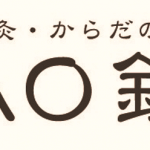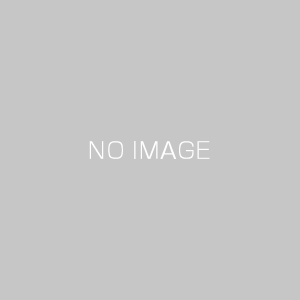あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
~あはき・柔整広告ガイドライン~
令和7年2月18 日
厚生労働省
目次
- Ⅰ.広告規制の趣旨 …………………………………………………………………………………. 1
- 1 趣旨……………………………………………………………………………………………….. 1
- 2 基本的な考え方……………………………………………………………………………….. 1
- (1) これまでの広告規制の考え方 ………………………………………………………….. 1
- (2) 今回の広告規制の考え方 ……………………………………………………………….. 2
- (3) 広告を行う者の責務 ………………………………………………………………………. 3
- (4) 禁止される広告等の基本的な考え方 ……………………………………………….. 3
- (5) 広告可能な事項の基本的な考え方 ………………………………………………….. 4
- 3 他の法律における規制との関係 …………………………………………………………. 4
- Ⅱ.広告規制の対象範囲 …………………………………………………………………………… 5
- 1 広告の定義……………………………………………………………………………………… 5
- 2 実質的に広告と判断されるもの ………………………………………………………….. 5
- 3 暗示的又は間接的な表現の扱い ………………………………………………………… 6
- 4 あはき・柔整に関する広告規制の対象者 ……………………………………………… 7
- (1) あはき・柔整に関する広告規制の対象者 …………………………………………… 7
- (2) 広告媒体との関係 …………………………………………………………………………. 8
- 5 広告に該当する媒体の具体例 ……………………………………………………………. 8
- 6 通常、あはき・柔整に関する広告とは見なされないものの具体例 ……………… 9
- (1) 学術論文、学術発表等 …………………………………………………………………… 9
- (2) 新聞や雑誌等の記事 ……………………………………………………………………… 9
- (3) 利用者等が自ら掲載する体験談、手記等 ………………………………………….. 9
- (4) 施術所内で掲示又は配布するパンフレット等 ……………………………………. 10
- (5) 利用者からの申し出に応じて送付するパンフレットや電子メール …………. 10
- (6) インターネット上の情報提供に関する基本的な考え方 ……………………….. 10
- Ⅲ.広告可能な事項について……………………………………………………………………. 11
- 1 あはき・柔整に関する広告として広告可能な範囲 ………………………………… 11
- 2 広告可能な事項の表現方法について ………………………………………………… 12
- (1) 広告の手段 ………………………………………………………………………………… 12
- (2) 広告可能な事項の記載の仕方 ………………………………………………………. 12
- (3) 略号や記号の使用 ………………………………………………………………………. 12
- 3 広告可能な事項の具体的な内容(あはき師法、柔整師法) ……………………. 13
- (1) 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所(あはき師法第7条第1項第1号、柔整師法第 24 条第1項第1号関係)及びあはき師の業務の種類(あはき師法第7条第1項第2号関係) ………………………………………………………. 13
- (2) 施術所の名称(あはき師法第7条第1項第3号、柔整師法第 24 条第1項第i2号関係)等 …………………………………………………………………………………. 13
- (3) 施術所の電話番号及び所在の場所を表示する事項(あはき師法第7条第1項第3号、柔整師法第 24 条第1項第2号関係) …………………………………. 15
- (4) 施術日又は施術時間(あはき師法第7条第 1 項第4号、柔整師法第 24 条1項第3号関係) ……………………………………………………………………………… 16
- 4 広告可能な事項の具体的な内容(その他厚生労働大臣が指定する事項) .. 16
- (1) あはき師法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨及び柔整師法第 19 条第1項前段の規定による届出をした旨 ………………………………….. 17
- (2) 医療保険療養費支給申請ができる旨 ……………………………………………… 17
- (3) 予約に基づく施術の実施及び休日又は夜間における施術の実施 ………… 18
- (4) 出張による施術の実施 …………………………………………………………………. 18
- (5) 駐車設備に関する事項 …………………………………………………………………. 18
- 5 あはき、柔整に関する内容に該当しない事項 ……………………………………… 19
- Ⅳ.禁止される広告等について …………………………………………………………………. 20
- 1 あはき師法、柔整師法上禁止される広告 ……………………………………………. 20
- (1) 広告可能な事項でない事項の広告 ………………………………………………… 20
- (2) 広告禁止事項の広告 ……………………………………………………………………. 20
- 2 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される広告 …………….. 21
- 3 その他虚偽誇大な表現等について ……………………………………………………. 23
- (1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)及び誇大な広告(誇大広告)………. 23
- (2) 他施術所等と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)及び公序良俗に反する内容の広告等 ………………………………………………………………….. 24
- 1 あはき師法、柔整師法上禁止される広告 ……………………………………………. 20
- Ⅴ.相談・指導等の方法について ………………………………………………………………. 26
- 1 指導……………………………………………………………………………………………… 26
- 2 苦情相談窓口の明確化 …………………………………………………………………… 26
- 3 消費者行政機関等との連携 …………………………………………………………….. 26
- 4 広告関連法令との関係 ……………………………………………………………………. 27
- 5 広告指導の体制及び手順 ……………………………………………………………….. 28
- (1) 広告内容の確認 ………………………………………………………………………….. 28
- (2) 広告違反の指導及び措置 …………………………………………………………….. 29
- (3) 告発の対象者 ……………………………………………………………………………… 30
- (4) 公表…………………………………………………………………………………………… 30
- Ⅵ.インターネット上のウェブサイト等について …………………………………………….. 31
- 1 基本的な考え方……………………………………………………………………………… 31
- (1) ウェブサイト等の原則的な取り扱いについて …………………………………….. 31
- (2) 広告に該当しないウェブサイト等の取り扱いについて …………………………. 32
- 2 本項目の対象 ………………………………………………………………………………… 33
- 3 自費による施術を行う施術所等がウェブサイト等に掲載すべき事項 ……….. 33
- (1) 表示される情報の内容について、利用者が容易に照会できるよう、問い合iiわせ先を記載する、あるいはその他の方法により明示すること …………….. 33
- (2) 自費の施術に係る施術の内容、通常必要とされる費用等に関する事項について、情報を提供すること ………………………………………………………………. 33
- (3) 自費の施術に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること ……………………………………………………………………………………….. 34
- 4 ウェブサイト等に掲載すべきでない事項 …………………………………………….. 34
- (1) 内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの …………………………………………………………………………………………….. 34
- (2) 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの …………………………. 35
- (3) 内容が誇大なもの又は施術所等にとって都合が良い情報等の過度な強調………………………………………………………………………………………………….. 35
- (4) 早急な受療を過度にあおる表現又は費用の過度な強調 ……………………. 36
- (5) 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、施術所等への受療を不当に誘導するもの …………………………………………. 36
- (6) 公序良俗に反するもの …………………………………………………………………. 37
- (7) 品位を損ねる内容のもの ………………………………………………………………. 37
- (8) あはき師法、柔整師法以外の法令で禁止されるもの …………………………. 37
- 1 基本的な考え方……………………………………………………………………………… 31
- Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について ………………………………………………… 38
- 1 基本的な考え方……………………………………………………………………………… 38
- 2 本項目の対象 ………………………………………………………………………………… 38
- 3 広告に掲載すべきでない事項 ………………………………………………………….. 38
- (1) 内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの …………………………………………………………………………………………….. 38
- (2) 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの …………………………. 38
- (3) 早急なサービスの利用を過度にあおる表現 …………………………………….. 38
- (4) 費用の過度な強調 ……………………………………………………………………….. 39
- (5) 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、事業所等へのサービス利用を不当に誘導するもの …………………………….. 39
- (6) あはき師法、柔整師法等に抵触する内容を含むもの …………………………. 39
- (7) 公序良俗に反するもの ………………………………………………………………….
- (8) 関連法令等で禁止されるもの ………………………………………………………… 39
iiiⅠ.広告規制の趣旨
1 趣旨
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下「あはき」という。)若しくは柔道整復業(以下「柔整」という。)又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という。)については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217 号。以下「あはき師法」という。)、柔道整復師法(昭和 45年法律第 19 号。以下「柔整師法」という。)、その他の規定により制限されてきたところであるが、今般、これらの規定の解釈及び運用を指針に定めることにより、利用者が適切な施術所及び出張による施術(以下 「施術所等」という。)を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、 広告の適正化の推進を図ることを目的とするものである。
また、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会における、あはき・柔整に関する不適切な広告を是正すべきとの意見や、消費者庁にあはき又は柔整の免許を有していない者等 (あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含み、以下「無資格者」という。 )による行為で発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、あはき・柔整に関する広告だけでなく、 無資格者による広告も含めた広告の在り方について、検討を行ったものである。
なお、今回の「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(以下「本指針」という。)において、 「あはき師」とは、あはき師法第1条に定める免許を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師をいい、 「柔整師」とは、柔整師法第3条に定める免許を有する柔道整復師をいうものとする。
2 基本的な考え方
(1) これまでの広告規制の考え方
あはき・柔整に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、あはき師法、柔整師法等により、限定的に認めらた事項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。
① あはき及び柔整は、人の身体に関わる施術であり、不当な広告により1利用者が誘引され、不適当な施術を受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。② あはき及び柔整は、専門性の高い施術であり、利用者がその文言から提供される実際の施術の質について事前に判断することは非常に困難であること。
(2) 今回の広告規制の考え方
① 本指針の作成に当たり、原則として限定的に認められた事項以外の広告が禁止されてきた、あはき師法及び柔整師法の規定する範囲内において、これまでの基本的な考え方は引き続き堅持しつつも、利用者が適切に施術所等を選択するために必要かつ正確な情報の提供を確保する観点からその運用の留意事項を定めることとした。
② 本指針Ⅱの1に掲げた広告の定義のうち③ (認知性) の要件との関係で、原則としてインターネット上のウェブサイト等(なお、SNSの書き込み等の取扱いについては本指針Ⅱの6(6)及びⅥの1(1)を参照
されたい。 )は、あはき師法及び柔整師法の広告規制の対象とはならないものの、インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状に鑑み、ウェブサイト等の内容の適切な在り方についても本指針に定めることにより、関係団体等による自主的な取組を促すこととした。
③ 無資格者による行為により発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、その広告の適切な在り方について、本指針に定めることとした。
④ 医療法(昭和 23 年法律第205号)第3条第1項において、「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、診療所、医院その他病院又は診療所に紛
らわしい名称を附けてはならない。」と規定していることから、医療と紛らわしい表記が認められないことは重要な点であり、本指針においては、これを十分考慮した上で広告可能な事項の例等を記載することとした。
⑤ 本指針では、上記②及び③に関する記載内容及び広告の適切な在り方を示すことから、あはき師法、柔整師法、医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。) 、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37年法律第 134 号。以下「景品表示法」という。 ) 、不正2競争防止法(平成5年法律第 47号) 、 健康増進法 (平成14 年法律第 103号) (以下、医療法、医薬品医療機器等法、景品表示法、不正競争防止法及び健康増進法を併せて「広告関連法令」という。 )等の関連法令による規制の対象に含まれる事項を含めることとした。
⑥ あはき及び柔整は人の身体に関わる施術であるため、利用者が安心・安全に施術を受けるためには、利用者が正しい情報に基づいて施術所等を選択できることが重要である。利用者が施術所等を選択する上で、その名称は重要な情報であることから、
・ 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
・ 法令に基づき都道府県に届け出られ適法であること
・ 医療機関と紛らわしい名称を用いていないこと
について利用者が正しく認知できる名称であることを必要とした。
⑦ 違法性が疑われる広告等に対して、都道府県等が指導等の措置を適切に実施できるよう、どのようなものが広告違反として問題となるかを明らかにするため、広告に係る基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や指導上の留意事項等を取りまとめた。
⑧ 本指針は、 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」 (平成30年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知別紙3。以下「医療広告ガイドライン」という。)を参考にしつつ、指導等の実効性を担保するとともに、診療を必要とする状態の者の適切な診療を受ける機会や施術所等の利用を希望する者の適切な施術を受ける機会の喪失が起こり得るような広告を規制の対象とするという考え方に基づき作成することとした。
(3) 広告を行う者の責務
あはき・柔整に関する広告を行う者は、その責務として、利用者が広告
内容を適切に理解し、適切な施術の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならず、また、施術所等が自らの責任により行う必要がある。
(4) 禁止される広告等の基本的な考え方
あはき・柔整に関する広告は、あはき師法第7条第1項又は柔整師法第
24条第1項の規定により広告が可能とされた事項以外は、何人も、 (文書その他) いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないこととされている。
3なお、 あはき師法及び柔整師法上広告が可能とされた事項や、 本指針Ⅱの1に示す広告の定義に該当しない情報についても、広告関連法令等又はそれら法令に関連する広告の指針に抵触する場合は、広告関連法令等による行政処分や罰則の適用となることに留意する必要がある。
さらに、内容が虚偽にわたる広告や比較優良広告等、あはき・柔整に関する広告としてふさわしくないものについても、ウェブサイト等の情報提供も含め、厳に慎むべきものである。これは、無資格による行為に関す
る広告についても同様の考え方で取り扱うべきものである。
(5) 広告可能な事項の基本的な考え方
あはき・柔整に関する広告として広告可能な事項は、 あはき師法及び 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る
事項」 (平成 11 年厚生省告示第 69 号。以下「あはき広告告示」という。)又は柔整師法及び「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項」 (平成 11年厚生省告示第70号。以下「柔整広告告示」という。)により、あはき・柔整に関する広告として広告可能な範囲に限られる。また、 広告に掲載される情報は、利用者の施術所等及び施術内容の選択(以下「施術選択等」という。)に資する情報であることを前提とし、その内容については、客観的な評価が可
能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。
3 他の法律における規制との関係
あはき・柔整に関する広告の規制については、あはき師法又は柔整師法の他
にも広告関連法令等があり、これらにおいては、あはき及び柔整の施術所等のウェブサイト等も規制対象となる。広告関連法令等に違反する広告は、当該法
令等に基づく行政処分や罰則の対象となり得るものである。
都道府県等によるあはき・柔整に関する広告の適正な取締りに当たっては、広告関連法令等の内容を十分に理解し、あはき師法又は柔整師法所管課室を中心に、景品表示法所管課室等の関係法令を所管する課室も含め、収集した情報の交換等により、密接に連携・協力し、指導等の実効性を高めるように努められたい。
なお、 これらの法所管課室が行う苦情相談や指導等の手順その他の実務的な内容については、本指針Ⅴを参照されたい。
4Ⅱ.広告規制の対象範囲
1 広告の定義
あはき師法第7条及び柔整師法第 24 条の対象となるあはき・柔整に関する広告の該当性については、次の①から③までの要件のいずれも満たす場合に該当するものと判断されたい。
① 利用者を施術所等に誘引する意図があること 【誘引性】
② 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること 【特定性】
③ 一般人が認知できる状態にあること 【認知性】
なお、①でいう「誘引性」は、施術者又は施術所の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば利用者が施術者又は施術所の依頼によらずに自発的に作成した体験手記や新聞記事等のメディア等は、特定の施術所等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。
また、②でいう「特定性」については、複数の施術者又は施術所等を対象としている場合も該当するものであること。③については、特に、インターネット上の情報提供との関係で問題になるため、本指針Ⅱの6の(6)及びⅥも参照すること。
2 実質的に広告と判断されるもの
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1の①から③までの要件に該当することを回避するために以下のような表現がなされる場合がある。しかし、下記ア~オのような場合で、実質的に上記1の①から③までの要件をいずれも満たす場合は、広告に該当するものとして取り扱うことが適当である。
ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、利用者を誘引するものではありません。」との記述があるが、施術所等の名称が記載されているもの
イ 「あはき師法又は柔整師法の広告規制のため、具体的な施術所等の名称は記載できません。」といった表示をしているが、住所や電話番号等から施術所等が特定可能であるもの
5ウ インターネット上の施術所等紹介(仲介)サイトあるいは口コミサイト
と称して、あたかも閲覧者の口コミ情報を基に取材したように当該施術所等を掲載したり、施術所等のランキング等を掲載しているが、施術所等が掲載料・広告料を支払っているものや、口コミによる取材の基準やラン
キング等の決定の基準が恣意的なものエ 施術法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の施術所等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイト等のURLが記載されていることで、一般人が容易に当該施術所等を特定できるものオ 新しい施術法等に関する書籍等の形態をとっており、当該書籍等では直接には施術所等が特定されず、「当該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等の記載があるが、 「当該施術法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」等と記載し、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると、特定の施術所等(複数の場合も含む。)をあっせんされるもの上記オは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるものであるが、 利用者に広告と気付かれないように行われるいわゆるステルスマーケティングについても、 施術者又は施術所が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼している等上記1の①から③までの要件を満たし、同様に広告として取り扱うことが適当な場合があるので、十分な留意が必要である。
3 暗示的又は間接的な表現の扱い
あはき・柔整に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的又は間接的にあはき・柔整に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のようなものは、あはき・柔整に関する広告に該当するので、広告可能とされていない事項を含む場合等は認められない。また、その他の広告関連法令等にも留意する必要がある。
ア 名称又はキャッチフレーズによるもの
(例)レディース鍼灸、レディースマッサージ「レディース○○」は、あはき師法第7条第2項、柔整師法第 24条6第2項で禁止されている施術方法や女性特有の疾患を暗示させる表現であり、認められない。
イ 写真、イラスト、絵文字、ロゴマークによるもの
(例)病人が回復して元気になる姿のイラスト効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、病気を治す技能を保証するとの誤認を与える恐れがあり、認められない。
ウ 新聞、雑誌等の記事、あはき師、柔整師、学者等の談話、学説、体験談等の引用又は掲載によるもの
(例)① 新聞が特集した施術方法の記事を引用するもの
施術方法の記事を引用するものは、あはき師法第7条第2項、柔整師法第 24 条第2項で禁止されている施術方法を暗示させる表現であり、認められない。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載自らの
施術所等や勤務するあはき師又は柔整師が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
③ 施術の効果に関する専門家の談話を引用するもの
施術の効果に関する専門家の談話は、その施術の効果があると暗示するものであるが、効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、その内容が保証されたものと著しい誤認を利用者に与えるおそれがあるものであり、広告は認められない。
エ 施術所等のウェブサイト等のURLや電子メールアドレス等によるもの
(例)
www.katakorinaoru.ne.jp
肩こり治る(katakorinaoru)とあり、肩こりが治癒することを暗示している。施術の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、施術の効果を保証しているとの誤認を与える恐れがあり、認められない。
4 あはき・柔整に関する広告規制の対象者
(1) あはき・柔整に関する広告規制の対象者
あはき師法第7条第1項において「あん摩業、マツサージ業、指圧業、7はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をして
はならない」と規定され、また、柔整師法第24条第1項において「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と規定さ
れている。したがって、施術者又は施術所だけでなく、マスコミ、広告代理店、いわゆるインフルエンサー及びアフィリエイター1等、何人も広告規制の対象とされるものである。また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外のサーバーにあるホームページ(本指針Ⅱの6の(6)に示す広告に該当するものに限る) や海外から発送・送信されるダイレクトメール・電子メール等)も規制の対象である。
なお、あはき師法第 12 条の2第1項に規定する届出を行っている者についても、同条第2項の規定により第7条が準用され、同法の広告規制の対象者となる。
(2) 広告媒体との関係
広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる者は、依頼を受けて広告依頼者の責任の下で作成し、又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が広告可能な事項であるか等、あはき師法及び柔整師法並びに本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合には、広告依頼者とともにあはき師法又は柔整師法及び本指針による指導等の対象となり得るものである。
5 広告に該当する媒体の具体例
本指針Ⅱの1において広告の定義を示しているところであるが、広告の規制対象となる媒体の具体例としては、例えば、次に掲げるものが挙げられる。
(例)
ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ、ポケットティッシュ等によるものを含む。)イ ポスター、看板(プラカード、建物、電車、自動車等に記載されたもの
を含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物による1 本指針において、 「いわゆるインフルエンサー及びアフィリエイター」とは、個人のホームページやブログ、SNS 等で商品やサービスを紹介し、広告料収入を得る者をいう。8もの
ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光によるものエ 情報処理の用に供する機器によるもの(電子メール、インターネット上のバナー広告、施術所等紹介(仲介)サイトの紹介ページ(本指針Ⅱの2のウに該当するものに限る) 、 リスティング広告2、動画広告、 SNS広告3等)オ 不特定多数の者への説明会、 キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの
6 通常、あはき・柔整に関する広告とは見なされないものの具体例
(1) 学術論文、学術発表等
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされることはない。これらは、特定の施術所等(複数の場合を含む。)に対する利用者を増やすことを目的としているとは認められず、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までの要件のうち、①の「誘引性」を有さないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものである。ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にダイレクトメールで送る等により、実際には特定の施術所等(複数の場合を含む。)に対する利用者を増やすことを目的としていると認められる場合には、①の「誘引性」を有すると判断し、①から③までの要件を満たす場合には、広告として扱うことが適当である。
(2) 新聞や雑誌等の記事
新聞や雑誌等の記事は、特定の施術所等(複数の場合を含む。)に対する利用者を増やすことを目的としているとは認められず、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までの要件のうち、①の「誘引性」を通常は有さないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものであるが、施術者が費用を負担する等して記事の掲載を依頼することにより利用者を誘引する場合には、いわゆる記事広告として、広告規制の対象となるものである。
(3) 利用者等が自ら掲載する体験談、手記等
利用者自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A施術所を推薦する手記を個人Xが作成し、出版物やしおり等により公表2 「リスティング広告」とは、広告サービスにお金を払って検索結果に表示できる広告のこと。検索エンジンの自然検索結果の上部や下部の広告枠に表示できる広告がリスティング広告となる。
3 「SNS 広告」とは、SNS の配信面を利用して、自社商品・サービスの宣伝を行うこと。
9した場合や口頭で評判を広める場合には、一見すると本指針Ⅱの1に掲げ
た①から③までの要件を満たすが、この場合には、個人Xが自発的にA施術所を推薦したにすぎず、 利用者を誘引したことにならないため、 ①の「誘引性」の要件を満たさず広告とは見なさない。
ただし、A施術所からの依頼に基づく手記であったり、A施術所から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものと判断し、広告として扱うことが適当である。また、個人Xが
A施術所の経営に関与する者の家族等である場合等、施術者又は施術所の利益のためと認められる場合には、①の「誘引性」を有すると判断し、広告として扱うものであること。なお、広告に該当する場合には、これらの
体験談、手記等は広告可能な事項でないため、広告することはできない。
(4) 施術所内で掲示又は配布するパンフレット等施術所内で掲示又は配布するパンフレット等はその情報の受け手が、利用者に限定される限り、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までの要件のうち、①の「誘引性」を満たすものではなく、情報提供や広報と解される。
(5) 利用者からの申し出に応じて送付するパンフレットや電子メール
個々の利用者からの申し出に応じて、その都度送付するパンフレットや電子メールは、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までの要件のうち、③の「認知性」を満たすものではなく、施術所等に関する情報や当該施術所等での施術法等に関する情報を入手しようとする特定の者に向けた情報提供や広報と解されるため、広告とは見なされない。
(6) インターネット上の情報提供に関する基本的な考え方
インターネット上の施術所等のウェブサイト等は、当該施術所等の情報を得ようとの目的を有する者が、自らURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため、本指針Ⅱの1に掲げた③の「認知性」を満たさないものとして、従来情報提供や広報として扱ってきた。これらについては、引き続き原則として広告とは見なさないこととする。ただし、本指針Ⅵに記載のとおり、バナー広告等(本指針Ⅵにおいて定義する。 )や SNS での書き込み等については、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこととする。インターネット上のウェブサイト等に関する考え方等については、本指針Ⅵを参照されたい。
10Ⅲ.広告可能な事項について
1 あはき・柔整に関する広告として広告可能な範囲
あはき師法第7条第1項において「あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない」と規定され、また、柔整師法第 24 条第1項において「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と規定されている。
〇あはきに関して広告可能な事項
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
一 もみりようじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、 きゆう師等に関する法律第九条の
二第一項前段の規定による届出をした旨
五 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が
必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項
〇柔整に関して広告可能な事項
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
一 ほねつぎ(又は接骨)
11二 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項
2 広告可能な事項の表現方法について
(1) 広告の手段
あはき師法及びあはき広告告示又は柔整師法及び柔整広告告示により
広告が可能とされた事項については、文字だけではなく、本指針Ⅱの3の暗示的又は間接的な表現により写真、イラスト、映像、音声等による表現も可能である。
(2) 広告可能な事項の記載の仕方
あはき師法及びあはき広告告示又は柔整師法及び柔整広告告示により広告が可能とされた事項に対しては、正確な情報が提供され、利用者によるその選択を支援する観点から、情報の受け手側である利用者の理解促進のために分かりやすい表現を使用したり、その説明を加えることは、望ましいことであり広告可能とする。
(例)
・医療保険療養費支給申請ができる旨
→「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」又は「一旦施術費用の全額を負担いただきますが、後で保険者に対してその費用の一部を請求することができます」
※本指針Ⅲの4(2)参照
(3) 略号や記号の使用
広告可能な事項について、社会一般で用いられていたり、広告の対象となる地域において、正確な情報伝達が可能である場合には、略号や記号を使用することは差し支えないものとする。
(例)
・ 一般社団法人 → (一社)
・ 電話番号 03-0000-0000 → ☎ 03-0000-0000
12また、当該記号やマークが示す内容を文字等により併せて標記することで、正確な情報伝達が可能である場合においては、記号やマークを用いても差し支えない。
3 広告可能な事項の具体的な内容(あはき師法、柔整師法)
(1) 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所(あはき師法第7条第1項第1号、柔整師法第 24 条第1項第1号関係)及びあはき師の業務の種類(あはき師法第7条第1項第2号関係)
「施術者である旨」又は「柔道整復師である旨」については、あはき師法第1条又は柔整師法第3条に規定する免許を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師である旨をあはき・柔整に関する広告に記載できるものであること。また、「国家資格保有」の表記も併せて広告することが可能であること。
① 広告可能な事項の例
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師(鍼師)、きゅう師(灸師)
イ 柔道整復師
ウ 上記のア又はイと併せて「国家資格保有」の表記
・あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)
・はり師(国家資格保有) ・きゅう師(国家資格保有)
・柔道整復師(国家資格保有)
② 広告不可な事項の例
(上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現)
ア 東洋医学療法、伝統鍼灸、漢方、整体、カイロ等といった、あはき・柔整以外の業務の種類や、これらの民間資格を保有している旨
イ 外国におけるあはき師、柔整師といった類似資格を保有又は経歴を有している旨
(2) 施術所の名称(あはき師法第7条第1項第3号、柔整師法第 24 条第1項第2号関係)等利用者が安心・安全にあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けるためには、利用者が正しい情報に基づいて施術所等を選択できることが重要である。利用者が施術所等を選択する上で、その名称は重要な情報であることから、
13・ 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
・ 法令に基づき都道府県に届けられ適法であること
・ 医療機関と紛らわしい名称を用いていないこと
について利用者が認知できる名称である必要があることとする。
① 広告可能な名称の例
ア 提供する施術業態を特定せずに「施術所(院) 」と表記すること
○○施術所(院) 等
※ ただし、 (1)に示した「国家資格保有」の表記についても併せて表示する等、 利用者にとって分かりやすい名称とすることが望ましい。
イ 提供する施術業態 (マッサージ、 はり、きゅう等)に「治療院(所)」「療院(所)」を付けること○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院、○○鍼灸治療所 等ウ マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること○○マッサージ、はり・きゅう○○ 等エ 施術所が併設されている場合等に併記すること○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院 等② 広告不可な名称の例上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現を以下に示す。
なお、これらの広告不可な表現については、例えば、英語にしたり、一般的に同じ意味と認識される別の用語・呼称を用いる等表現方法を変えても表示は不可であること、また、看板、掲示物及び装飾等を含め
施術所外への表示も不可であることに留意すること。
ア 「病院又は診療所等」と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、○○(施術業態を含まない)治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック 等※ 診療科名や診療行為等と紛らわしい表現を含む名称も不可
イ あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称
カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート 等
ウ 提供する施術業態が混ざっている名称
○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院 等14エ 対象者を限定するもの○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門 等オ 施術内容・技能・方法を含んでいる名称東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法 等
カ 効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、 (施術が優良であることを示す意味で)巧み 等
キ 広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院 等ク その他,施術所と分かりにくい名称○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所 等
(3) 施術所の電話番号及び所在の場所を表示する事項(あはき師法第7条第1項
第3号、柔整師法第 24 条第1項第2号関係)施術所等の電話番号及び所在の場所を表示する事項については、利用者の便宜を図るためのものについては、広告可能とすること。
① 広告可能な事項の例
ア 電話番号にはFAX番号も含まれること
イ フリーダイヤルである旨
ウ 電話の受付時間 等
エ 所在の場所には郵便番号、最寄駅等からの道順及び所要時間、案内図、地図等が含まれること
オ 情報の伝達に関する事項(電子メールアドレス、ウェブサイトの
URL、QRコード 等)
② 広告不可な事項の例
(上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現)
ア 施術者の技能等広告可能でない事項を暗示する電話番号のルビ「1374(痛みなし)」 、「3776(みな治る)」等15(4) 施術日又は施術時間(あはき師法第7条第 1 項第4号、柔整師法第 24 条1項第3号関係)
施術日及び施術時間は、利用者に対し提供するべき情報であるので、可能な限りあはき・柔整に関する広告においても記載するのが望ましい。
ただし、医療と紛らわしく、診療を必要とする状態の者の適切な診療をける機会や施術所等の利用を希望する者の適切な施術を受ける機会を阻害するおそれがある表記は認められない。
① 広告可能な事項の例ア 時間による施術内容の別(例えば、 「午前施術・午後出張施術」等)イ 受付時間、施術曜日、休日(休療日)ウ 施術のほか初検、再検、往療、施療と表記すること(例えば、往療日、施療日、施療時間 等)
② 広告不可な事項の例(上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現)
ア 診療(診療日、診療時間、診療中 等)と表記すること
イ 診察(診察日、診察時間、診察中 等)と表記すること
ウ 診(休診日、初診、再診、往診 等)と表記すること
4 広告可能な事項の具体的な内容(その他厚生労働大臣が指定する事項)
その他厚生労働大臣が指定する事項(あはき師法第7条第 1項第5号、柔整師法第 24 条1項第4号関係)に関する広告可能な事項の具体的な内容は告示で定めている。
あはき広告告示 柔整広告告示
一 もみりようじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律第九条の二第一
項前段の規定による届出をした旨
五 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な
旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 柔道整復師法第十九条第一項前段の
規定による届出をした旨
三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申
請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項
16(1) あはき師法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨及び柔整師法第
19 条第1項前段の規定による届出をした旨
① 広告可能な事項の例
都道府県知事へ施術所開設に係る届出をした施術所である旨(例)○月○日 ○○県 開設届出済
② 広告不可な事項の例
(上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現)
厚生労働省認定・認可、指定
都道府県知事認定・認可、指定
(2) 医療保険療養費支給申請ができる旨
① 広告可能な事項
医療保険療養費支給申請ができる旨の表示 (利用者の理解促進の観点から、 「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」 又は「一旦施術費用の全額を負担いただきますが、後で保険者に対してその費用の一部を請求することができます」と言い換えることは可能とする。 )は、以下の要件を満たす場合に限る。
ア あはきの施術所等については、医師の同意が必要な旨を明示す場合に限ること
イ 柔整の施術所等は、脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限ること。なお、その際、 「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫等が医療保険療養費支給申請の対象となる」ことと、「このうち、脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要である」こととを併記することは差し支えない。
② 広告不可な事項の例
(上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現)
「各種保険取扱い」、「労災保険取扱い」、 「自賠責保険取扱い」、「交通
事故取扱い」等
※ これらは、医療保険療養費支給申請とは関係がないと考えられ
ることから広告不可な事項である
17(3) 予約に基づく施術の実施及び休日又は夜間における施術の実施施術を提供する日時等については、利用者に対し提供するべき情報であるので、可能な限りあはき・柔整に関する広告においても記載することが望ましい。
① 広告可能な事項の例
予約優先である旨 等
※ FAX、電子メール等で予約を受け付けている場合はその旨
(4) 出張による施術の実施
出張による施術の実施については、日時等についても利用者に対し提供するべき情報であるので、可能な限りあはき・柔整に関する広告においても記載するのが望ましい。ただし、医療と紛らわしく、診療を必要とする状態の者の適切な診療を受ける機会や施術所等の利用を希望する者の適切な施術を受ける機会を阻害するおそれがある表記は認めないこと。
① 広告可能な事項の例
ア 出張可能な範囲・地域
イ 出張に応じる施術者名
ウ 出張に対応する時間等(午前、午後の別を含む)
エ 往療と表記すること
オ 「訪問施術の実施」の表現
② 広告不可な事項の例
(上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現)
訪問診療、往診 等、「診」と表記すること
(5) 駐車設備に関する事項
駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している場合には当該駐車料金について広告可能であること。
① 広告可能な事項の例
駐車場の有無、場所、写真、料金、収容可能台数 等185 あはき、柔整に関する内容に該当しない事項はき・柔整に関する広告については、あはき師法及びあはき広告告示又は柔整師法及び柔整広告告示により広告が可能とされた事項以外の広告が禁じられているが、以下のア~オに示す背景等となる画像や音声等については、通常、あはき、柔整に関する内容ではないので、特段制限されるものではない。ただし、風景写真であっても、他の施術所や医療機関の建物である場合やそのような誤認を与える場合、あるいは、芸能人が当該施術所等を推奨することや芸能人が受療をしている旨を表示(音声によるものや暗示を含む。)することは、あはき・柔整に関する広告の規制の対象として取り扱うこと。
(例)
ア 背景等となる風景写真やイラスト(町や海の写真、山や森のイラスト)等
イ レイアウトに使用する幾何学模様 等
ウ BGMとして放送される音楽、効果音 等
エ 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日 等
オ 芸能人や著名人の映像、声、サインや写真 等
芸能人や著名人が、施術所等の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えないが、実際に当該施術所等の利用者である場合には、芸能人等が利用者である旨は、広告可能な事項ではなく、あはき・柔整に関する広告として認められないものとして扱うこと。
19Ⅳ.禁止される広告等について
1 あはき師法、柔整師法上禁止される広告
(1) 広告可能な事項でない事項の広告
あはき師法第7条第1項において「あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない」と規定され、また、柔整師法第24条第1項において「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と規定されており、あはき・柔整に関する広告は、利用者の施術選択等に資する情報として、あはき師法及びあはき広告告示又は柔整師法及び柔整広告告示により広告可能とされた事項を除いては、広告が禁じられている。なお、広告可能な事項については、本指針Ⅲを参照すること。
(2) 広告禁止事項の広告
また、あはき師法第7条第2項において「前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」と規定され、また、柔整師法第 24 条第2項において「前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」と規定されていることから、
施術者の技能、施術方法又は経歴に関する広告は一切認められないこと。
ア 施術者の技能、施術方法
(例)胸部疾患の灸、慢性病の根本治療、難病治療の専門、慢性疼痛治
療、高い技術、唯一の技術 等○○流指圧、痛くない鍼、気持ちの良いお灸、○○流接骨術 等イ 施術者の経歴
(例)○○養成校卒業後 中国○○大学にて学位取得○○療法の第一人者である○○先生に師事米国公認○○資格 ○○年取得
○○会員、○○研修修了
○○学会会員、○○代表(役員)
○○(有名人)のトレーナー 等
20<参考>
◎あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(広告の制限)
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又は
これらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左
に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
◎柔道整復師法
(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他
いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をして
はならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合において
も、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
2 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される広告
他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガ
イドラインも遵守すること。
① 医療法
医療法第3条第1項は、「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けては
21ならない。」と規定しており、施術所等の名称を病院又は診療所に紛らわしい名称とすることを禁止している。
② 医薬品医療機器等法
例えば、医薬品医療機器等法第 66 条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、効能・効果性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第 68条の規定により、承認前の医薬品・医療機器・再生医療等製品について、その名称や、効能・効果、性能等についての広告が禁止されており、例えば、そうした情報をウェブサイト等に掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
③ 健康増進法
例えば、健康増進法第 65条第1項の規定により、何人も、食品として販売に供する物に関して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすること禁止されており、そうした情報をウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
④ 景品表示法
例えば、商品又は役務の品質その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの若しくは事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(以下「優良誤認表示」という。)が禁止されている(同条第1号)。また、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(以下「有利誤認表示」という。)が禁止されている(同条第2号)。優良誤認表示又は有利誤認表示に該当する内容をウェブサイトに掲載
した場合には、当該規定等により規制され得ること。
22⑤ 不正競争防止法
例えば、不正競争防止法第 21 条第3項の規定により、不正の目的をもて役務の広告等にその役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止されている(同項第1号)ほか、虚偽の示をする行為が禁止されており(同項第5号)、例えば、虚偽の内容に当たるものをウェブサイト等に掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
3 その他虚偽誇大な表現等について
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)及び誇大な広告(誇大広告)仮に広告可能な事項に関する広告であったとしても、それが虚偽にわたったり、誇大なものである場合、誤った情報や誤認により、利用者を不当
に誘引し、不適切な施術を受けさせるおそれがある。虚偽にわたる広告とは、施術時間、休日、駐車可能台数、提供する施術業態(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復)等について、
事実に相違する広告を意味するものである。また、誇大な広告とは、必ずしも虚偽ではないが、施術時間、休日、駐車可能台数、提供する施術業態(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復)等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものである。 「人を誤認させる」とは、常識的に一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があると判断されることを意味し、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。
その内容が、虚偽又は誇大な広告については、当然、広告するべきではなく、また、広告関連法令等により罰則の適用対象となり得る。
(例)
① 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
・ 実際には、土日祝日は施術の受付をしていないのにも拘わらず、 「休日も朝から晩まで対応します!」や「年中無休」と表示するもの
・ 実際には、 深夜時間帯は施術の受付をしていないのにもかかわらず「24 時間施術」と表示するもの
・ 「都道府県知事の許可取得済み」「厚生労働省認可施術所」と表示するもの
→ 施術所はあくまで届出を要するものであり、都道府県知事の許可や厚生労働省の認可があるとの表示は広告可能な事項でないことに加え、事実と相違する広告である。23
・ 県内に他の施術所が存在するのに「県内で唯一の保険適用施術所」と表示するもの
・ 実際には、東京都内でしか出張による施術をしていないにも拘わらず、「関東地方への出張施術対応中」と表示するもの
・ 実際には、新人の施術者が施術をするにも拘わらず、「出張施術はすべて○○○○(院長)が施術します!」と表示するもの
・ 実際には、駐車料金が発生するにも拘わらず、「無料駐車場あり」と表示するもの
② 誇大な広告(誇大広告)
・ どんなお客様も医療保険療養費支給申請ができます。→ 筋肉痛、肩こり等には保険適用されないため、どんな場合も保険が適用されるとの表現は誇大広告として取り扱うべきである。
・ 知事へ届出済みの優良施術所です!→ 都道府県知事へ施術所の開設届をすることは、法における義務で
あり当然のことであるが、届出をしたことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な施術所であるかのような誤認を与える場合には、誇大広告である。
(2) 他施術所等と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)及び公序良俗に
反する内容の広告等
仮に広告可能な事項に関する広告であったとしても、比較優良広告、公序良俗に反する内容の広告、品位を損ねる内容の広告は、あはき・柔整に関する広告として適切ではなく、広告すべきでない。比較優良広告は、客観的な事実であったとしても、優秀性については広告可能な事項ではない上に、誤認を与えるおそれがあるため、広告関連法令等の規制対象にもなり得る。また、利用者に対して、施術者又は施術所等が、他の施術者又は施術所
等より優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと。あはき・柔整に関する広告は、利用者が広告内容を適切に理解し、施術等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものであることから、公序良俗に反する内容や、施術所等や施術の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある内容を広告することは許されない。
24(例)
① 他施術所等と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
・ 県内で唯一、○○に対応しています!
・ 出張施術はここだけ
② 公序良俗に反する内容
わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等
③ 品位を損ねる内容の広告
・ 保険適用でとってもお得に施術が受けられます!!
・ 交通事故無料
・ 来院はムダ!いつでも出張施術します!
・ 今だけ駐車料金2時間無料キャンペーン
25Ⅴ.相談・指導等の方法について
1 指導
あはき・柔整に関する広告の指導については、都道府県、保健所及び権限委
譲を受けた市町村等が行う。
ここでいう指導とは、広告の違法性を指摘し、是正に導くことであり、療養費等の適正化を念頭において、是正案を提示し、時間を経て結果を評価するまでをいい、指示するのみであったり、指導の時点で排除を目的としてはならない。
行政は、指導に当たり、通告無しに施術所等を訪問できるが、施術所等の利用者に配慮しなければならない。
担当部局が現地に赴くのが物理的に困難であれば、所在地を所管する都道府県・保健所や市町村が相互に協働されたい。
2 苦情相談窓口の明確化
あはき・柔整に関する広告が、利用者に対する客観的で正確な情報伝達の手段となるよう広告を実施する者に対する相談支援を行うとともに、虚偽・誇大な広告等により、利用者が適切な施術の機会を喪失したり、不適切な施術を受けることのないよう利用者からの苦情を受けるための担当係を決め相談窓口を明確化されたい。
具体的な窓口としては、保健所のあはき師法、柔整師法担当部署(以下「施術所開設等届出受付担当部署」という。)等が想定されるが、各都道府県、保健所設置市又は特別区の判断により、適切な苦情相談の体制を確保し、当該苦情相談の窓口の連絡先については、自治体のウェブサイトや広報誌等を通じて地域住民に周知するべきである。あはき・柔整に関する広告を実施する者からの相談窓口と利用者からの苦情相談の窓口は、別々であったり、他の業務との兼任は差し支えないが、実際に施術所等や広告代理店等を指導する担当者も含めて、相互に情報を共有し、一体的な相談・指導が効果的になされるよう適切な運用に努められたい。
3 消費者行政機関等との連携
あはき・柔整に関する広告又は無資格者の行為に関する広告に関して、利用者からの苦情は、管内の消費生活センターに寄せられることもあるので、苦情・相談の状況について、定期的に情報交換する等、消費者行政機関との連携に努め、違反が疑われる広告に関する情報を入手した際には、速やかに必要な措置26を講じられるよう情報共有のための連携体制を確立されたい。
4 広告関連法令との関係
景品表示法は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」 (景品表示法第5条第1号)及び「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」(同条第2号)等を規制している。すなわち、虚偽広告及び誇大広告等については、それが実際のもの等よりも著しく優良であると示すこと等により、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる場合には、同時に景品表示法に違反する可能性がある。医療法においては、「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 」(医療法第3条第1項)と規定されている。すなわち、施術所等の名称を病院又は診療所に紛らわしい名称とすることを禁止している。医薬品医療機器等法においては、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(医薬品医療機器等法第 66 条第1項)、「何人も、第14条第1項、第 23条の2の5第1項若しくは第 23条の2の 23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第 14条第1項、第19 条の2第1項、第23条の2の5第1項、第 23 条の2の17第1項、第 23 条の 25 第1項若しくは第 23 条の 37 第1項の承認又は第 23 条の2の 23 第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」(医薬品医療機器等法第 68条)とされ、医薬品、医療機器等の虚偽・誇大広告、承認前の医薬品等の広告を禁止している。健康増進法においては、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事27項(次条第3項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」(健康増進法第 65条第1項)と規定されている。これらの広告に関する規定は、重畳的に適用され得るものであるので、あはき師法又は柔整師法に違反し、又は違反が疑われる広告等が同時に広告関連法令等に違反していることが疑われる場合については、 都道府県等におけるこれらの法令の所管課室がそれぞれ連携しながら指導・処分等を行う等、所要の取組を効果的に行われたい。その際、違反事例に対して、一部の法令のみによる処分とするか、それぞれの法令で処分するかは、事例に応じて考えるべきであるが、他法令に違反するとの理由や他法令に基づく処分を受けるとの理由で、あはき師法又は柔整師法の広告違反が免責されることはない。他法令にも抵触する広告である場合にも、あはき師法、柔整師法や本指針による必要な指導等を適切に実施されたい。
5 広告指導の体制及び手順
あはき・柔整に関する広告に対する指導の措置は、各都道府県、保健所設置市又は特別区において、個別の事例に応じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対応すべきものであるが、あはき、柔整に関する法律等について相当の知識が求められることから適切な体制を作る必要がある。
(1) 広告内容の確認
本指針を参考に、あはき・柔整に関する広告として認められるものであるか等を判断することになるが、広告可能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等は、常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考えられる。このため、違法性が疑われる広告等に対する相談や指導に当たっては、
① まずは、施術所開設等届出受付担当部署等において、あはき師法、柔整師法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると判断できる広告については、広告を行う者に対して改善指導等を行う
② 施術所開設等届出受付担当部署等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別できない広告については、その内容について、 (別添1)の様式により、都道府県等の職員から厚生労
働省医政局医事課あてに電子メール等によって照会するという手順を採るようお願いする。28また、あはき師法、柔整師法や本指針に違反していると判断できる広告について、広告を行う者(法人の場合は、主たる事務所)が自らの管下の地域にない場合については、必要があると認める場合は、当該広告物及び入手できた広告の内容の根拠に関する資料等を添えて、広告を行う者が存在する地域を所轄する都道府県、保健所設置市又は特別区あてに速やかに報告されるようお願いする。広告を行う者の所在が不明である場合や海外の事業者等である場合には、厚生労働省医政局医事課あてに報告いただくようお願いする。
(2) 広告違反の指導及び措置
以下に参考として、広告違反の指導及び措置について具体的に記載するが、各都道府県等が個別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべきものであり、以下のような手順に限定されるものではないこと。
ア 行政指導
施術所開設等届出受付担当部署等は、第三者や内部の者からの通報等を端緒としてあはき師法、柔整師法や本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した場合には、任意の調査として、当該広告又は情報物に記載された施術者又は施術所に対して、説明を求める等により必要な調査を行うこと。任意の調査により、あはき師法、柔整師法や本指針に違反することを確認した場合、あるいは、明らかにあはき師法、柔整師法や本指針に違反する広告を発見した場合には、当該違反広告については、通常はまず、
① 行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正することを訪問・電話又は文書等により、あはき・柔整に関する広告を行っている施術者又は施術所に求めること。その際、目安となる是正期間を設けること。さらに必要に応じて違反広告物の回収、廃棄等を指導すること。
② 本指針Ⅱの4に示したように、施術者又は施術所だけでなく、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局、公共施設、宿泊施設、商業施設等の広告を作成した者や広告を掲載した者も広告規制の対象となることから、必要に応じて調査や指導を行うこと。
③ 指導の実施後、一定期間を経過しても指導に基づく是正がなされていなければ、当該違反広告の責任者等に対して、 (別添2)に示す様式を参考とした報告書の徴収(あはき師法第10条1項、柔整師法29第 21 条1項) 、書面による改善指導等の行政指導としての措置を講ずること。
イ 告発
アに示したように、違反広告を発見した場合には、通常はまず、行政指導により当該違反広告の中止や内容の是正を求めることとなるが、① 違反広告を行った者が中止若しくは是正の行政指導に従わない場合
② 違反広告を繰り返す場合
③ 報告の求め(あはき師法第 10条1項、柔整師法第 21条1項)に対して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合には、刑事訴訟法(昭和 23年法律第 131号)第239条第2項の規定により、司法警察員に対して書面により告発を行うことを検討すること。なお、罰則については、30 万円以下の罰金(あはき師法第 13 条の
8第1号又は6号若しくは柔整師法第 30条第5号又は7号)が適用される。
ウ 受領委任の取扱いに係る地方厚生局等への通知上記イにより罰金刑に至った施術者については、 「健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」と規定されている受領委任協定又は契約違反となるため、施術
所開設等届出受付担当部署等は、管轄である都道府県及び地方厚生局に通知を行うこと。
(3) 告発の対象者
告発の対象者は、違反広告の実施者が、個人である場合には当該個人であるが、施術所の場合には、その開設者とし、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局、公共施設、宿泊施設、商業施設等の場合には、その代表者とし、それらの者に加え、法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等を事例に応じて対象とすること。
(4) 公表
刑事告発等を実施した際には、必要に応じて、事例を公表することにより、利用者や住民等に対して当該違反広告に対する注意喚起を行うこと。
30Ⅵ.インターネット上のウェブサイト等について1 基本的な考え方
(1) ウェブサイト等の原則的な取り扱いについて
本指針Ⅱの6(6)のとおり、 原則としてウェブサイト等は、 あはき師法、柔整師法の規制対象となる広告には該当しない。もっとも、 以下のアからウのように、 本指針Ⅱの1に掲げた①から③までの要件を満たすものについてはこれに該当し、あはき師法、柔整師法の規制対象となる。
ア バナー広告等
インターネット上のバナー広告、検索サイト上で例えば「鍼灸」を検索文字として検索した際にスポンサーとして表示されるもの、検索サイトの運営会社等に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの、 施術所等口コミサイトと称して、あたかも閲覧者の口コミ情報を基に取材したかのように当該施術所等の情報を掲載したり、施術所等のランキング等を掲載しているもので、施術所等が掲載料・広告料を支払っているものや、 口コミによる取材の基準やランキング等の決定の基準が恣意的なもの等(以下「バナー広告等」という。)については、実質的に本指針Ⅱの1に掲げた①から③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。この場合、バナー広告等にリンクしている施術所等のウェブサイト等についても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針Ⅱの1に掲げた③の要を満たすものであり、さらに本指針Ⅱの1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。
イ SNS での書き込み等
SNSでの書き込み等については、公開範囲が限られていないものと、公開範囲が限られているものがある。
公開範囲が限られていない場合には、公開時から一般人が認識可能な状態であることから、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。公開範囲が限られている場合に関しても、公開時においては公開範囲に含まれる者のみが閲覧することとなるが、SNSの性質上、公開範囲に含
31まれる者が自ら当該書き込み等の情報を求めるものではない上、閲覧者が、当該書き込みについて何らかの反応を起こすことで、2次的、3次的に伝達されることから、本指針Ⅱの1に掲げた③の要件を満たすものであり、さらにⅡの1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。
ウ その他
上記ア及びイの他、以下の例に示すようなインターネット上の情報については、実質的に本指針Ⅱの1に示す①誘引性、②特定性及び③認知性のいずれの要件も満たす場合には、法の規制対象となる広告として取り扱うものであること。また、上記の条件を満たして広告として規制の対象となった下記の例示を入り口として閲覧するウェブサイト等についても、広告として規制される媒体と一体であることから規制対象となる広告として取り扱うものであること。
(例)
・ インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果等に連動して表示されるスポンサー等に関する情報
・ 検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果
・ 施術所紹介サイト上の紹介ページ
・ リスティング広告
・ 動画広告
(2) 広告に該当しないウェブサイト等の取り扱いについて
また、 インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状に鑑み、あはき師法、柔整師法の規制対象となる広告に該当しないウェブサイト等についても、その内容の適切な在り方について、本指針に定め、本指針により関係団体等による自主的な取組を促す。具体的には、利用者にとって有用な情報源の一つとなっているウェブサイト等特有の性格等も踏まえつつ、
・ 利用者保護の観点から、不当に誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項
・ 利用者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、通常必要とされる施術内容、費用、施術のリスク等のウェブサイト等に掲載すべき事項を以下のとおり示すこととした。医療広告ガイドラインでも指摘されていることからも、本指針を踏まえ、施術所等においても、営利を目的として、 ウェブサイト等により利用者を不当に誘引することは厳に慎むべきであり、利用者保護の観点も踏まえ、 ウェブサイト等に掲載されている内容を利用者が適切に理解し、施術を選択できるよう客観的で正確な情報提供に努めるべきである。
2 本項目の対象
本項目は、インターネット上の施術所等の情報全般を対象とするものであるまた、本指針は、原則として、当該施術所等に勤務する者等が個人で開設する、いわゆるブログ等の内容を対象とするものではないが、当該施術所等のウェブサイト等のリンクやバナーが張られている等、当該施術所等のウェブサイト等と一体的に運営されている場合等には、本指針の内容を踏まえ、利用者を不当に誘引することがないよう十分に配慮すべきであること。
3 自費による施術を行う施術所等がウェブサイト等に掲載すべき事項以下の情報の掲載場所については、当該情報を閲覧する者にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを貼った先のページへ掲載したり、利点・長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用することは控えること。
(1) 表示される情報の内容について、利用者が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載する、あるいはその他の方法により明示すること
(2) 自費の施術に係る施術の内容、通常必要とされる費用等に関する事項について、情報を提供すること
自費による施術は、医療保険療養費による施術とは異なり、その内容や費用が施術者又は施術所等ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点が重要であること。標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる施術の最低金額から最高金額までの範囲を示す等して可能な限り分かりやすく示すこと。また、回数券やプリペイドカード等を販売する場合には、その商品の内容や契約内容を利用者が正確に理解して購入できるよう表示すること。
(3) 自費の施術に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること自費施術に係る主なリスク、副作用等に関する事項、標準的な費用や施術期間・回数を掲載する等して、利用者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。
4 ウェブサイト等に掲載すべきでない事項
(1) 内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないものウェブサイト等に掲載された内容が虚偽にわたる場合、利用者に著しく事実と相違する情報を与え、利用者を不当に誘引し、診療を必要とする状態の者の適切な診療を受ける機会や施術所等の利用を希望する者の適切な施術を受ける機会を喪失させるおそれがあるため、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
なお、ここで掲げるものは例示であって、他の場合であっても本指針の対象となり得ること。
(例)
・ 絶対安全な施術です。絶対に治る施術。
→ 絶対安全な施術等は、あり得ないので、虚偽広告として扱うこと
・ どこへ行っても治らなかった方、 諦めないで当院へお越しください。
・ 本当によくなりたいと思っている方、何とかしてみせます。
・ 治ります、元気・健康にします、根本治療、自信があります、〇〇を解決します、○○に効きます、○○の治癒率○○%、理想の体重に、負担をかけずにピンポイントで矯正。
・ 痛みのない骨盤矯正、痛くない独自の整体術で驚きの効果、安心安全・確かな技術。
・ からだにやさしい、穏やかな手技療法。
・ 厚生労働省認可○○専門術
・ 加工・修正した施術前・施術後の写真等の掲載
→ あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した施術前・施術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべきであること。
・ 「○%の満足度」「改善率〇%以上」「〇%の人が効果を実感」「たった1回で効果を実感」「顧客満足度 No1」
→ 体験談、治療効果に関する表現又は最上級表現については、情報の有用性が限定的であり虚偽広告として取り扱うべきであること。
(2) 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
「日本一」、「No.1」、「最高」等、特定又は不特定の他の施術所等と自らを比較の対象とし、提供する施術の内容等について、自らの施術所等が他の施術所等よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について利用者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるものであり、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。併せて、ウェブマッピング等において、自らの施術所等が他の施術所等よりも優良であるような情報を掲載するため、利用者に謝礼を支払う又は依頼する等して、自らの施術所等に便益を与えるようなコメント等を掲載させるべきではないこと。また、著名人との関連性を強調する等、利用者に対して他の施術所等より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、利用者を不当に誘引するおそれがあることから、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
(例)
・ 口コミサイトで1位を獲得。
・ 全国優良〇〇院。
・ ○○にも掲載された
・ 著名人も当施術所で施術を受けております。
→ 優良誤認(他の施術所等より著しく優れているとの誤認)を与えるおそれがあり、芸能人等が受療している旨は、事実であっても、広告可能な事項ではない。
(3) 内容が誇大なもの又は施術所等にとって都合が良い情報等の過度な強調
① 任意の専門資格、施術所認定等の誇張又は過度な強調
当然の事実等の誇張又は過度な強調や、活動実態のない団体による資格認定の名称、当該施術所等の機能等について利用者を誤認させるような任意の名称は、不当に誘引するおそれがあることから、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
② 施術の効果・有効性を強調するもの
撮影条件や被写体の状態を変える等して撮影した施術前、施術後の写真等をウェブサイト等に掲載し、その効果・有効性を強調することは、利用者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写35真等については内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。また、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した施術前、施術後の写真等については、上記(1)の虚偽の内容に該当し、あはき師法、柔整師法以外の法令で規制され得るものであること。
③ 施術者又は施術所等にとって便益を与える体験談の強調施術者又は施術所等にとって便益を与えるような感想等のみを意図的に取捨選択し掲載する等して強調することは、利用者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるものであり、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。また、利用者に謝礼を支払う等して、施術者又は施術所等にとって便益となるような感想等のみが出されるように誘導し、その結果をウェブサイト等に掲載することについても、同様に行うべきでないこと。
④ 提供される施術の内容とは直接関係ない事項による誘引
提供される施術の内容とは直接関係のない情報を強調し、利用者を誤
認させ、不当に誘引する内容については、ウェブサイト等に掲載すべき
でないこと。
(4) 早急な受療を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
利用者に早急な受療を過度にあおる表現、費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、利用者を不当に誘引するおそれがあることから、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
(5) 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、施術所等への受療を不当に誘導するもの科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、以下のア)~ウ)のように、利用者の不安を過度にあおる等して不当に誘引することは、厳に慎むべき行為であり、そうした内容については、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
ア)特定の症状に関するリスクを強調することにより、施術所等への受療を誘導するもの
(例)
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受療くださ
イ)特定の施術の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する施
術の実施へ誘導するもの
(例)
・ 「○○術は効果が高く、おすすめです」
ウ) 特定の施術等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する施術以外のものへ誘導するもの
(例)
・ 「○○術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○術をおすすめします」
(6) 公序良俗に反するもの
わいせつ・残虐な図画・映像、差別を助長する表現等の公序良俗に反する内容については、ウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
(7) 品位を損ねる内容のもの
施術所等や施術の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきでないこと。
(8) あはき師法、柔整師法以外の法令で禁止されるもの
ウェブサイト等への掲載に当たっては、本指針Ⅳの2に例示する規定を含め、広告関連法令等も併せて遵守すること。
Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について
1 基本的な考え方
これまで、消費者庁に対し、国家資格を有していない者による行為で発生した事故の情報が多く寄せられてきた。平成 24 年8月2日に独立行政法人国民生活センターが公表した資料では、施術所等を利用したきっかけ等について、家族や知人の紹介が最も多かったが、情報誌や雑誌広告、チラシ等を見て選択したという相談も多く、また、当該広告には、適応症の広告や、身体症状・疾病に効果があると受け取られるような広告等消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれがある広告や、あん摩マッサージ指圧以外の行為を提供する場所において、「マッサージ」という語句を用いた広告等がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがあると指摘されている。
現在においても、 無資格者の行為に係る不適切広告等の情報等が寄せられていることから、あはき、柔整の他に無資格者の行為の広告の適切な在り方について、本指針に定めることとしたものである。
具体的には、 利用者にとって有用な情報源の一つとなっている広告の性格等も踏まえつつ、利用者保護の観点から、不当に誘引する虚偽又は誇大な内容等の広告に掲載すべきでない事項を示すこととした。
消費者庁に事故の情報が多数寄せられている現状からも、本指針を踏まえ、事業所等においては、営利を目的として、広告により利用者を不当に誘引することは厳に慎むべきであり、利用者保護の観点も踏まえ、広告に掲載されている内容を利用者が適切に理解し、あはき、柔整又は無資格者の行為を選択できるよう、客観的で正確な情報提供に努めるべきである。
2 本項目の対象
無資格者の行為に関する広告として、本項目の対象となるのは、本指針Ⅱの4(1)と同様とし、関係団体等による自主的な取組を促すものである。
3 広告に掲載すべきでない事項具体的には以下のとおりである。
(1) 内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの
(2) 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
(3) 早急なサービスの利用を過度にあおる表現
(4) 費用の過度な強調
利用者に対して費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、 利用者を不当に誘引するおそれがあることから、本指針での広告やウェブサイト等に掲載すべきでないこと。
(5) 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、事業所等へのサービス利用を不当に誘導するもの
(6) あはき師法、柔整師法等に抵触する内容を含むもの
無資格者の行為は、国家資格が必要なあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務とは全く異なることから、国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は
不適切であり、 これは、 写真、画像等を用いた場合においても同様である。また、「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現は、特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いことから、広告及びウェブサイト等に表現すべきでないものである。
(7) 公序良俗に反するもの
(8) 関連法令等で禁止されるもの本指針での広告やウェブサイト等への掲載に当たっては、Ⅳの2に例示する規定を含め、広告関連法令等を遵守すること。
(別添1)
あはき師法第7条又は柔整師法第 24 条の規定違反が疑われる広告等について
(照会)
厚生労働省医政局医事課あて
都道府県等名
1.広告等の対象となった施術者等の氏名又は施術所等の名称、所在地
名 称:
所在地:
2.広告等の発見時期 年 月 日
3.広告等の発見経緯
4.広告等を行った者
名 称:
住 所:
連絡先:
その他:(広告等の対象となった者との関係等)
5.広告等の主な内容
6.違反が疑われる事項
7.広告等の対象者や広告実施者への調査状況
広告対象者: 有 ・ 無
広告実施者: 有 ・ 無
8.調査した内容及び指導状況
9.厚生労働省に確認したい事項
10.担当者名及び連絡先
担当者名:
所属部署名:
電 話:
11.その他
※照会する広告又は疑いのある情報物の写しや写真等、入手できた広告等の内容の根拠に関する資料を添付すること。
※電子メールによる照会を原則とするが、映像や音声による広告等や送付する量が多く容量が非常に大きなファイルを添付する等、電子メールにより難い場合には、あらかじめ医政局医事課の担当者に相談すること。
(別添2)
年 月 日
報告書(あはき師法、柔整師法広告違反関係)
都道府県知事 ○○ ○○ 殿
(保健所設置市長、特別区長)
住所(施術所等の所在地)
氏名(施術者(開設者)の氏名)
1.施術所等の概要
施術所の開設年月日又は出張による業務の届出年月日:
受領委任の取扱いに係る届出状況(届出年月日、施術管理者名等) :
2.違反を指摘された日時、場所等
3.媒体名及び年月日
(※指摘を受けた媒体以外の違反広告に使用した媒体名及び年月日も併せて記載)
4.指摘を受けた字句等及び適用条項
5.違反広告を行った経緯、原因、理由等
(※法律の認識不足、営業上の理由、管理体制の不備等、違反となった経緯、原因、理由等を具体的かつ詳細に記載)
6.講じた措置
(※媒体への連絡、当該広告及び原版の回収破棄等の状況を記載し、パンフレット等の場合は、回収状況、作成部数及び年月日、配布先、配布部数及び年月日も併せて記載)
7.広告に対する反省並びに今後違反を繰り返さないための対策及び方針